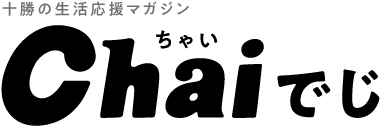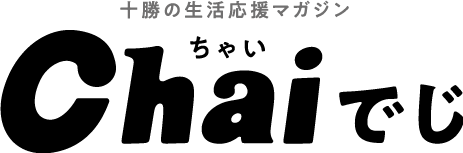夏本番!旨辛メニュー(3)「辛さと健康豆知識~帯広大谷短期大学 林千登勢さん」
<教えてくれた人>
夏にほしくなる「辛み」について教えて!
味覚に含まれない「辛み」
味覚には甘味、塩味、酸味、苦味、うま味という「5つの基本味」があります。この中に辛みが含まれていないことにお気づきですか?味覚は舌にある味蕾(みらい)で感じますが、辛みは皮膚の痛覚や温度覚の複合作用で感じており、「味」ではなく「刺激」なのです。つまり辛さそのものに「おいしさ」を感じることはありません。
辛いだけでないトウガラシの効能
トウガラシの主な辛み成分「カプサイシン」には、さまざまなパワーがあります。摂取することでエネルギーの代謝を向上させ、唾液の分泌を促して食欲アップにつなげる効果も。また発汗作用によって体温を下げるので、暑い日に辛い料理を食べるのは理にかなっていますね。またわずかにビタミンCが含まれているほか、抗菌作用もあります。
辛さでハイになる!?
最近は外国のグルメを気軽に楽しめることもあって、辛い料理が流行していますね。激辛メニューを平気で平らげる若者も増えている気がします。カプサイシンには神経を興奮させる作用があるので、ヤミツキになってさらなる刺激を求めてしまうのかも?どうか「辛いものハイ」による食べ過ぎには気を付けてくださいね。
もっと知りたい!辛いものQ&A
Q.辛さの耐性は人種によって異なる?
A.東南アジアなどで暮らす人々は、もともと辛さに強いというイメージがあります。そのような仮説を検証すべく、アメリカ国立衛生研究所では欧米系、アフリカ系、アジア系などの被験者を集めて、辛さの感じ方を比較しました。関連する遺伝子を調べた結果、人種によって大きな変異は見られないとのこと。つまり食生活によって辛さの耐性が付いたのであり、本来の感じ方は一緒のようです。
Q.辛い料理を食べるとやせる?
A.カプサイシンにはエネルギー消費を高め、脂肪を付きにくくする作用があります。1982年に京都大学で行われた実験によると、カプサイシンを与えたラットの交感神経は活性化され、代謝が高まることが分かりました。また続けて摂取すると、食べる行為自体が生み出すエネルギー消費DIT(食事誘発性熱産生)や安静時代謝も高まります。ただし効果は小さいので、過度な期待は禁物です。
Q.辛いものは体に悪い?
A.適度な辛み成分の摂取は胃の粘膜を保護したり、味付けのアクセントにして塩分を控えたりするのに役立ちます。しかし激辛料理などでトウガラシを大量に食べた場合、カプサイシン感受性神経が麻痺して胃粘膜が損なわれやすくなります。コショウやショウガなどの辛み成分も同様です。特に幼い子どもは辛さ成分への耐性が低いので注意しましょう。
Q.ワサビの辛さとトウガラシの辛さの違いは?
A.トウガラシに含まれる「カプサイシン」は、コショウ、ショウガ、サンショウなどの辛み成分と化学構造が似ており、揮発性に乏しいのが特徴。一方ワサビの辛み成分「アリルイソチオシアネート」はカラシなどにも含まれ、揮発性があります。揮発性が乏しいと長くヒリヒリとした辛さになり、揮発性があれば短時間で消える爽やかな辛みとなります。
【参考文献】
「スパイスなんでも小辞典」(講談社)日本香辛料研究会編、「素敵なトウガラシ生活」(柏書房)渡辺達夫著、「とうがらしの世界」(講談社)松島憲一著
※フリーマガジン「Chai」2025年7月号より。
※写真の無断転用は禁じます。
夏本番!旨辛メニュー
今年も超HOTな夏がやって来た!夏になると恋しくなるのが辛い料理。思い切り頬張り、汗をかき、厳しい暑さを乗り切ろう!